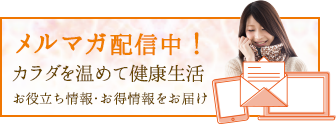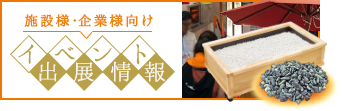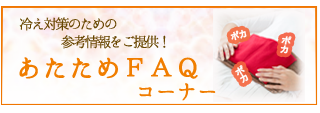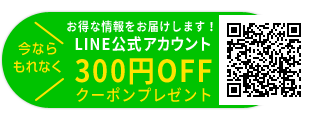参考情報:“体を温める”ことの大切さと冷え対策
健康維持において、“体を温める”ことは基本です。
“体を温める”ことの大切さと冷え対策をテーマに、参考情報を提供いたします。
※学説や定説は、研究成果や臨床結果などにより日々変更され、進化発展していきます。
書かれていることや教えられたことをそのまま鵜呑みにするのではなく、必ずご自身でも調査および勉学を継続し、常にアンテナを立てておくことを心掛けるようにしてください。
就寝時の足先の冷えには足首を温める
寒い夜。足先が冷えてなかなか寝付けない。
そんな方も少なからずいらっしゃるかと思います。
対策として、靴下を履いて寝るというのがまず思いつく手法です。
ただこの手法は、そのときの体調や靴下の種類などによって、メリットにもなりデメリットにもなります。
【就寝時の靴下着用のメリット】
例えば、お風呂から出てだいぶ時間が経ってしまうと足先は冷え冷えになってしまっています。
再びお風呂や足浴するのは面倒なので、靴下を履いて温めて寝る、というパターンになりますが、しっかり温まればそれでよいと思います。
単純に、手早く温めることができる、というのが靴下のメリットです。
【就寝時の靴下着用のデメリット】
逆にデメリットもあります。
一般的な靴下は締め付けの強めなものが多いため、血流が滞ったり、汗をかいて蒸れることで必要以上に熱が奪われたりして、逆に冷えてしまう、というケースが多々発生すると想定されます。
蒸れは衛生上もよくありません。
しかしながら、個人的な経験を踏まえて言いますと、靴下を履いて寝ることの最大のデメリットは “熱がこもってしまい、良質な睡眠がとれないこと” だと思います。
一般的に、お風呂から出たあと、余剰熱が抜けていくときに副交感神経が優位になり、そこがスムーズに睡眠に入れるベストなタイミングだと言われています。
足先にこの理論を当てはめると、靴下を履き続けることで産まれた余剰熱を抜く必要がある、ということになり、その場所は足の先と足の裏です。
通気性のよくない靴下で足先から足裏まですっぽり覆われてしまっていると、余剰熱が放熱されずに体内にこもってしまい、よい睡眠がとれず、夜中に目が覚めてしまったり、快適な朝を迎えられなかったり、ということになる場合があります。
こういった経験をされた方も、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
就寝時の足先の冷えには足首を温める
そこでおすすめなのが “足首を温める” です。
冷えは3首から入りやすいと言われています。首、手首、そして足首です。
皮膚が薄い部位である、大きな血管が皮膚の近くを通っている、がその大きな理由ですが、ツボがあることもその理由のひとつです。
足首でいうと、内側のくるぶしの少し上に三陰交があり、冷えの緩和を司るツボとされていて、サポーターなどでここをしっかり押さえ温めることが大切です。
サポーターの選択時のポイントとしては、“血流を考慮した、ゆったりフィットで締め付けないものを選ぶ” ことですね。

このようにズラして使えば、余分な熱の放熱のために足先だけ出して、足首周りをしっかりと温めることもできます。

お尻回りから下、下半身全体が冷えるという方は、まず内臓を温めて深部体温を上げる必要がありますので、腹巻やお腹・お尻・腰回りをスッポリ包んで温めるウォーマーパンツの併用をおすすめします。

人の体は十人十色で、体調も日々変わるので、一概には言えませんし、冬でもある程度温暖な地域と雪の降る極寒な地域など居住環境の違いもあるので、靴下を履いて寝るのがちょうどよい、という方もいるでしょう。
大切なのは、人体の基本的な仕組みを理解した上で、自身の体の特徴を知り、自分に合った冷え対策を練ることです。
2017.10.31更新
2015.11.17